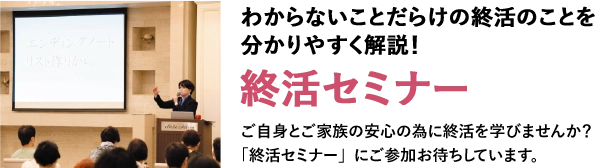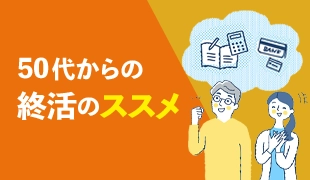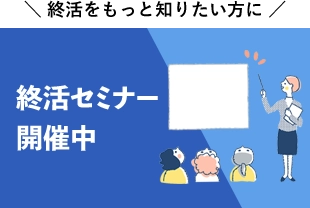「お葬式って、何のためにあるんでしょう?」
これは、ある60代の女性からいただいた質問です。
ご主人を亡くしたばかりの方でした。
葬儀を終えたあと、彼女はぽつりとこう言いました。
「ただ時間に追われて、形だけ済ませてしまった気がするんです。もっと何か、伝えたかったのに。」
こんにちは。終活コーディネーター/グリーフケア士の吉原友美です。
このお言葉が、ずっと私の胸に残っています。
葬儀とは、単なる「お別れの場」ではなく、“気持ちを届ける場”でもあります。
亡くなった方に「ありがとう」を伝えると同時に、残された人の心を整える時間でもあるのです。

ところが、近年では時間の制約や費用の事情などから、葬儀の簡略化が進んでいます。
「家族葬」「直葬」など、儀式を極力省いたスタイルも一般化しています。
もちろん、これらの選択肢にも意味があります。
けれども、“心が追いつかない葬儀”になってしまっては、本来の役割が果たされません。
良い葬儀とは何か……?
私が関わったある家族葬では、こんな演出がありました。
棺のそばには故人の趣味だった釣り道具。
壁には生前の笑顔の写真が何枚も飾られ、好きだった演歌が静かに流れていました。
親族がそれぞれ、思い出話を一言ずつ語る時間も設けられていました。
涙が自然にこぼれ、でもどこかあたたかい雰囲気。
参列者が帰るとき、誰もが「いいお式だったね」と口にしていたのがとても印象的でした。

これは、グリーフケアの観点でもとても理想的な葬儀です。
グリーフとは「喪失による心の痛み」のこと。
そしてグリーフケアは、その痛みに寄り添い、回復の手助けをするケアのことです。
人は、大切な人を失ったとき、すぐに気持ちを切り替えることはできません。
でも、想いを語り合ったり、故人の存在を再確認したりする時間があると、心は少しずつ整理されていきます。
だからこそ、葬儀は「ただ送り出す」場ではなく、“心を通わせる時間”であってほしいのです。
心を通わせるお別れの形とは?
最近では、「偲ぶ会」や「メモリアルパーティー」のように、形式にとらわれずに故人を偲ぶ方法も広がってきました。
好きだったカフェで集まったり、思い出の場所で写真を眺めたり……。
小さな工夫で、心の満足度は大きく変わります。
大切なのは、「自分らしい別れ方」を選ぶこと。
そして、「残された人の心を支える時間をつくること」です。

“良い葬儀”とは、必ずしも盛大なものではありません。
参列した人が、帰り道でふっとあたたかい気持ちになれる。
故人の存在を改めて思い出せる。
そんな葬儀こそが、本当に心に残る葬儀だと私は思います。
もし、これからご自身やご家族の終活を考えるときが来たら、
「自分らしく、心を通わせる別れ方ってどんなだろう?」と、少し想像してみてください。
葬儀は、人生最後のセレモニーであると同時に、
愛や感謝を伝える“人生のエピローグ”でもあります。
涙だけじゃない、笑顔や感謝、あたたかい空気が流れるような、そんな別れのかたちが、これからの時代にはもっと増えていくことを願っています。